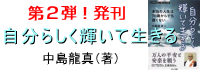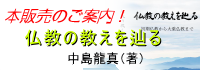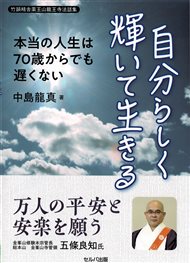本当の人生とは、すべての人と幸せに願う、天清寺
| 令和6年度の法話 |

11月の法話「あの世での歓喜を目指して」
| あの世での歓喜を目指して 本日はご参拝頂き有難う御座います。今年も早いもので車のタイヤ交換や庭の冬囲いなど、雪に備えて冬支度をしなければならない季節になりました。 仏教では多くの方々に支えられ生かされている自分を認識し、報恩感謝の実践として世のため人のため、更には生きとし生けるもの全てに慈悲の心を抱いて善業を積みなさいと教えています。 初期経典の「ダンマパダ」では善を成そうとする時は急ぎなさい。躊躇していると心は悪事に走り出してしまうと教えています。そして、人として生を授かったからには花を繋いで華鬘を作るように、一つでも多くの善業を積む努力をしなさいと教えています。 善業を積むためには先ず身口意の三業を整えることが重要だとして、行為や言動を慎み、その根底にある思いを慎んで善業の実践に結び付けなさいと教えています。そうしたことを実行できればその成果として善業を積んだ人はこの世で歓び、あの世でも歓べ、二つの世界で歓ぶことができる。そして、自分の成した行為が清浄な心に支えられていたことに満足し歓喜できると説いています。 新聞やテレビでは連日のように強盗や殺人などの暗いニュースを報じていますが、人間として誕生できたからには一つでも多くの善業を積む努力を重ねたいものです。 これから始まります皆様方の新しいひと月が善業を積む毎日で満たされ、あの世でも歓喜できる日々となりますようご祈念申し上げます。本日はご参拝頂き誠に有難う御座いました。 令和6年11月 天清寺 |
10月の法話「慈しみの心を堅持する」
| 慈しみの心を堅持する 本日はご参拝頂き有難う御座います。今の日本では亡き人を供養し成仏を願うのが仏教のように思われていますが、それはあくまでも方便であってお釈迦様の教えではありません。初期仏教の経典の中でもお釈迦様の教えを色濃く伝えていると言われる「スッタニパータ」では他人から批判されるような行いをせず、一切の生きとし生けるものが幸福であれ、安穏であれ、安楽であれと願う気持ちを常に堅持しなさいと教えています。 また、あたかも母が自分の独り子を命を懸けて護るように、一切の生きとし生けるものに対し、無量の慈しみの心を持ちなさいとも教えています。そして、そうした慈しみの心を立っている時も、歩いている時も、座っている時も、横になっている時も、眠っていない限り常に心に抱き、忘れてはならないと教えています。これこそこの世に人間として生を授けて頂いた私達が目指すべき生活の指針ではないでしょうか。 私達が信仰しています金峯山修験本宗では管長猊下ご発願のもと、世界中の人々が良くなるようにと「万人安楽とも祈り」を実践しています。自分の願いを叶えるための祈りではなく、ご縁ある方々が良くなるように、この世の人々が皆さん良くなるようにと祈っているのです。こうした輪を広げて行くことでこの世を仏の世界に一歩近づけることが出来るのではないでしょうか。 これから始まります皆様方の新しいひと月が生きとし生けるもの一切が幸福であれ、安穏であれ、安楽であれと祈る日々で満たされますようご祈念申し上げます。本日はご参拝頂き誠に有難う御座いました。 令和6年10月 天清寺 |
9月の法話「北海道マラソンに想う」
| 北海道マラソンに想う 本日は暑い中、ご参拝頂き有難う御座います。境内の家庭菜園ではトマトやキウリが豊作で、無農薬で育てた新鮮な野菜が食卓を飾ってくれ、贅沢な食事をさせて頂いています。 先日、札幌で恒例の北海道マラソンが開催されました。自坊近くの新川通りを走りますので、沿道で応援する人の「頑張れ、頑張れ!」と叫ぶ大きな声が聞こえて来ました。 その人は特定の選手を応援しているのではなく1時間以上もの間、走って来る選手みんなに声を掛けていました。我が宗が「みんなようなれ」と実践している「万人安楽とも祈り」と同じように、全ての選手が良い走りが出来るようにと声援を送っていたのです。選手の方々も熱い声援に励まされて大きな力を頂いたのではないでしょうか。今回のマラソンではコースを走る選手と沿道で応援する人とは途中で交代することはありませんが、人生で考えますとある時は応援する立場であっても、次の時には応援されながら走る立場になることだってあり得ます。 今回の北海道マラソンでは参加者が申告した完走予想時間に合わせ背番号が割り当てられ、背番号順に並んでスタートしましたので整然としたランナーの流れが出来、狭い道路でも2万人近い参加者が渋滞することなく走ることが出来ました。 人生はそうは行きません。遅い人が先にいたり、道案内や給水所がなかったりと条件が違いますし、走行距離も人それぞれ違って来ます。そうした中で助けたり助けられたりしながらゴールを目指して休むことなく走り続けることになります。この世に生を授けられた全ての人々が互いに応援し合い支え合って、人生と呼ばれるそれぞれのコースを立派に完走できるよう心よりご祈念申し上げます。本日はご参拝頂き誠に有難う御座いました。 令和6年9月 天清寺 |
8月の法話「仏教徒の心構えとは」
| 仏教徒の心構えとは 本日は暑い中ご参拝頂き有難う御座います。境内の家庭菜園で取れる夏野菜が食卓を飾ってくれる季節になりました。無農薬の新鮮な野菜が毎日頂けるので本当に有難いです。 今月のお盆にはお墓参りをしてご先祖様に手を合わせ、お経を唱える方も多いのではないでしょうか。それで今日はお経の最初に唱える「開経偈」についてお話させて頂きます。「開経偈」は中国で作られましたが仏教では宗派を問わず唱えるお経です。 無上甚深微妙法 百千万劫難遭遇 我今見聞得受持 願解如来真実義 という28文字の非常に短いお経です。和訳しますと、この上なく深遠で優れた仏の教えは無限といえる程の時間を掛けても出会うことは難しいのです。ところが私は今、その教えを見たり聞いたりする機会を得ました。この貴重な機会を活かして教えの真実を理解し体得したいと願っています。との意味になります。 そもそも人間として生まれて来たこと自体が有難いのですが、こうして尊い教えを授けられたことは奇跡に近いのです。先ずそうした自覚を持つことが大切であり、ご縁を活かして尊い教えを学び具体的な行動に結び付けて実践しなければなりません。お経を唱える前に「開経偈」を読誦することは、実践実行の決意表明であり、お経を唱える者の心構えを遵守する誓願でもあります。 「経読みの経知らず」との諺がありますが、お経を唱えても実践が伴わなければ単なる発生練習になってしまいます。そうならないよう心掛けたいものです。これから始まります皆様方の新しいひと月が仏教の教え実践の日々となりますようご祈念申し上げます。本日はご参拝頂き誠に有難う御座いました。 令和6年8月 天清寺 |
7月の法話「極楽浄土を目指す」
| 極楽浄土を目指す 本日はお忙しい中、ご参拝頂き有難う御座います。歳を取りますと心身の健康を守るための努力が必要になります。毎日の生活を充実させ意義あるものにするためには常に前向きに考え、何事にも積極的に取り組む意欲が大切になりますが、歳を取りますと意欲が低下してしまいます。そこで私は毎朝、有縁の人達の幸せを祈りドーパミンの分泌を促して意欲の向上を図るようにしています。また、天気の良い日は家庭菜園の仕事をして日光を浴びセロトニンの分泌を促して心身共にリラックスできるよう努めています。 毎朝、礼拝に続いて最初に唱えるお経が「懺悔文」です。「懺悔文」は華厳経の普賢行願品にある偈文で我昔所造諸悪業 皆由無始貪瞋痴 従身語意之所生 一切我今皆懺悔 という28文字のとても短い経典です。和訳致しますと「私が昔から作ってきた様々な悪い行いは始めが分からない程、遠い昔から行ってきた貪りや怒り、無知による愚かさなどの三毒を原因とするもので、それらは行動や言動、思いなどによって生じたものです。私は今それら全てを懺悔致します」となります。とても分かりやすい内容ですが仏教の教えは生活の中で実践して始めて学んだことになるのです。これまでに犯してしまった悪業を解消するためには先ず過去を反省し、その証として善業を積むしかありません。そうすることで新たな第一歩を踏み出せるのではないでしょうか。元気な体と自由な時間を授けて頂いているのですから、今日一日を大切にして新たな悪業を作らず、世の為人の為に過ごせるよう精進を重ねて参りましょう。 これから始まります皆様方の新しいひと月が「懺悔文」実践の日々で満たされ、極楽浄土に繋がる日々となりますようご祈念申し上げます。本日はご参拝頂き誠に有難う御座いました。 令和6年7月 天清寺 |
6月の法話「本当の終活を目指す」
| 本当の終活を目指す 本日は貴重な週末ご参拝頂き有難う御座います。今年も早いもので半年が過ぎようとしています。家庭菜園のために植えたトマトやえんどう豆、二十日大根などの種が全て芽を出し、元気に成長を続けてくれています。野菜に負けないためにはどのように過ごせば良いのでしょうか。その答えを仏教が教えてくれています。 「スッタニパータ」は紀元前3世紀以前に成立した経典ですが、その中でも最も古い部分とされていますアッタカ・ヴァッガ(第四章)では人間としてどのように生きるべきかを簡潔明瞭に、しかも具体的に教えてくれています。そこで強調されています教えは次の5点です。一つは欲望を捨て執着を離れて正しく生きるための見解と智慧を持つことです。智慧と言いますと私達は知識や問題解決能力などを思い浮かべますが、仏教で説く智慧とは自分の心相に通達することであり、心を冷静に観察し、心の有様を良く知り見極めることだと教えています。二つ目は怠ることなく勤め励んで心して学ぶことです。三つ目は多くを求めず衣食の量を知ることです。四つ目は他人と争わず腹を立てることなく発する言葉を慎むことです。五つ目は他人との比較を止め、常に謙虚で傲慢にならないことです。そして、修行者は心の内に平安を求めるべきであり、外に求めはならないと教えています。心を平静に保つことは無感動になることではありません。恵まれ満たされていることへの感謝の気持ちを常に忘れず維持することが大切です。 当たり前と思っていないでしょうか。時間を無駄にしていないでしょうか。他人と比較して考えたり行動したりしていないでしょうか。美味を求めて満腹になるまで飲食していないでしょうか。本当の終活とはこうしたことがないよう自分を見つめ、仏教の教えを守れるよう精進することではないでしょうか。 これから始まります皆様方の新しいひと月が本当の終活を目指した日々となり、心の平静を獲得できる毎日となりますようご祈念申し上げます。本日はご参拝頂き誠に有難う御座いました。 令和6年6月 天清寺 |
5月の法話「授けられた道を歩む」
| 授けられた道を歩む 本日はゴールデンウイークの中ご参拝頂き有難う御座います。毎年この時期になりますと思い出すことがあります。34年前にゴールデンウイークを利用して尺八演奏のためアメリカに行きました。ハーバード大学など5ヶ所で演奏したのですが、ベルチャタウンの学校で演奏した際、教育委員の方から記念品として額に入れた詩を頂きました。有名なロバート フロストの「The road not taken」と題した詩でした。「森の中で道が二つに分かれていました。良く考えて片方の道を選び歩んで来ました。その結果今の自分があるけれども、行かなかった道もあった」という内容の詩です。 私達の人生も詩のように常にどちらに進むか選択を求められています。大きくは進学や就職・結婚などですが、小さくは毎日のようにあれか、これかと常に選択を迫られています。分かれ道に差し掛かると、どちらかひとつの道を選ぶことになります。長い人生の中で歩むべき道を常に自分で選び進んで来たと思ってしまいますが、果たしてそうでしょうか。道を選ばせてくれるのも縁であれば、道を選んだことで体験させられる人との別れや新たな出会いも縁です。お釈迦様は縁起の法則を唱えられました。この世の人生は縁で成り立っていると言っても過言ではありません。不要な縁など一つもないのです。今の自分に取って必要だからこそ縁を頂くことが出来たのです。縁が無ければどんなに求めても願いを叶えることは出来ません。縁によって私には私に取って最もふさわしい道が授けられているのです。そう思って授けられた道を大切に歩むことしかありません。そうすることで次の新たな人生の展開が生まれ、心豊かな日々を送ることができるのではないでしょうか。 これから始まります皆様方の新しいひと月が授けられた道を感謝して受け止め、最善を尽くして歩める日々となりますようご祈念申し上げます。本日はご参拝頂き誠に有難う御座いました。 令和6年5月 天清寺 |
4月の法話「塞翁が馬に学ぶ」
| 塞翁が馬に学ぶ 本日はご参拝頂き有難う御座います。3月にまとまった雪が降ったり、寒い日が続くなどして雪解けが遅くなりましたが、今年もいつものように希望に満ちた春がやって来ました。 科学が発達し月の世界で暮らすことも夢でなくなりつつありますが、自然の脅威は今も昔も何一つ変わっていないように感じます。世界中の人々の平穏な日常生活を突然奪ってしまったコロナウイルスの出現や能登半島を襲った地震など、予想もしなかったことが起こっています。 コロナ禍により受けた経済的な打撃は大きく、苦難を強いられた方々も多いと思いますが、コロナ禍によって気付かされたり、それまでの風習が見直されたこともたくさんあります。リモートワークの普及もその一つではないでしょうか。サラリーマンの方々に取りましては通勤する必要が無くなると同時に、家族の居る家で一日を過ごすことができるようになりました。こうした時間を利用して家族との過ごし方を見直したり、自身の向上のために取り組むことができればこれまで以上に心豊かな毎日を送ることができます。能登半島地震の場合も、この機会に災害に強く暮らしやすい地域造りを実現できれば輝かしい未来に繋がることになります。 「人間万事塞翁が馬」という諺があり、幸か不幸かはその時々の状況だけでは判断できず、本当のことは長い目で見なければ分からないと教えてくれています。これから始まります皆様方の新しいひと月が降り掛かる困難を乗り超え「塞翁が馬」のように最後は幸せに繋がる日々となりますようご祈念申し上げます。本日はご参拝頂き誠に有難う御座いました。 「塞翁が馬」とは中国の塞翁という老人の馬が逃げてしまったので悲しんでいると、逃げ出した馬が駿馬を連れて帰って来たのです。喜んでいると連れて来た馬に乗っていた息子が落馬して足の骨を折ってしまいました。悲しんでいると戦争が始まり元気な男性は徴兵されることになりましたが、怪我をしていた塞翁の息子は徴兵を免れ命拾いしました。 令和6年4月 天清寺 |
3月の法話「原因我に有りを再認識」
| 原因我に有りを再認識 本日はご参拝頂き有難う御座います。先月の下旬に11年振りに風邪をひき4日間寝込むことになりました。お弟子さん達と計画した尺八の吹き初め会やキワニスクラブに依頼された卓話の予定を間近に控えてのことでした。ベッドに横になりながら、何故このタイミングで風をひかなければならないのだろうかと、腹立たしい気持ちになりました。 仏教では人生の避け難い苦しみとして生老病死の四苦を説いています。薬を飲んでは横になる状態の中で、まさに仏教の教えを想い起こす4日間でした。昼寝など一切しない私ですが朝昼晩と、いつでも横になると直ぐに寝られることの不思議さを感じますと共に、いかに日頃、体を酷使していたかを痛感させられました。 雪まつりの雪像作成チームとしてアメリカのポートランドから来た人達をお世話していたワイフが風邪にかかり、治ったワイフと入籍記念日に朝里川温泉に一泊旅行に出掛け、今度は私が同じような症状になってしまったのでした。 吹き初め会でお弟子さんから「先生、免疫力が弱っているんですよ」と言われ、ハットしました。それまで風邪にかかったのはワイフのせいだと思っていましたが、そうではなく私の体に原因があったのだと気付かされました。今年は雑務を避け、自分の年齢や体力にふさわしい日常生活を送るよう心掛けて参りたいと思っていますが、どうなることでしょうか。不安が残ります。 これから始まります新しいひと月が「原因我に有り」を常に念頭にして行動できる日々となりますよう、お互いに精進を重ねて参りましょう。本日はご参拝頂き誠に有難う御座いました。 令和6年3月 天清寺 |
2月の法話「在家信者の模範とは」
| 在家信者の模範とは 本日は雪の中、ご参拝頂き有難う御座います。仏教では仏教徒を在家と出家とに大別し、それぞれに対して修行の方法や守るべき戒律を説いています。私達のように在家の者が仏教徒にふさわしい日々を過ごすためにはどのようなことに心掛け生活すれば良いのでしょうか。 「雑阿含経」の一切事経でお釈迦様は在家信者のあるべき姿について教えを説いています。そこではまず在家信者であるためには仏法僧の三宝に帰依し、八法を守って実践に励まなければならないとしています。在家信者が守るべき八法とは ① 強い信仰の気持ちを持つこと ➁ 五戒を守ること ③ すすんで布施を行うこと ➃ 出家修行者の教えを良く聴くこと ⑤ 聴いた教えを身に付け保持すること ⑥ 常に冷静に自分を見つめ道をはずさないこと ⑦ 現状に満足せず理想に近づけるよう努力すること ⑧ 更に上を目指して真理を追究し実践すること 以上の八法を守り実践することができてもそれに満足せず、更に縁のある人達にも守らせ実践させるよう勧めなさいと教えています。こうしたことを日々の生活の中で実践できれば、在家信者でありながら出家修行者の上に立つことができると教えています。 これから始まります皆様方の新しいひと月が常に八法実践の日々となり、在家信者の模範となる毎日になりますようご祈念申し上げます。本日はご参拝頂き誠に有難う御座いました。 令和6年2月 天清寺 |
1月の法話「体で守る七戒と心を守る三戒」
| 体で守る七戒と心を守る三戒 本日は正月のお忙しい中、ご参拝頂き有難う御座います。皆様に取りまして今年一年が平穏で実り多い年になりますようご祈念し、初護摩を焚かせて頂きました。一年の計は元旦にありと申しますが、正月を迎え今年一年の目標を立てられた方も多いのではないでしょうか。 「安般守意経」では仏法は学び知ることに終わってはならない。学んだことを具体的に行為として実践しなければ学んだことにはならないと教えています。また、学んだことを実践し体得することこそが仏教が求める真理の道だとも教えているのです。そして、修行する者は仏道の根幹となすものを目指して修行しなければならないとし、仏道の根幹とは心であり、思いであり、意識そのものだと説いています。これらは見ることも聞くことも出来ないが、言動や行動を支える根源的なものであり、善き人になるためには欠くことの出来ないもので、仏道修行の根幹をなすものだと断言しています。 このように最も大切な心を正しく維持するためには先ず体を安定させる必要があると教えています。そして、体を安定させ新たな罪障を積むことがないように不殺生・不偸盗・不邪淫・不両舌・不悪口・不妄語・不綺語の七戒を守りなさいと説いています。こうして体を整えることが出来たら次に貪りを捨て、怒りをこらえ、妬むことがないよう心を守るための三戒を遵守して心を正しく保ち、安らぎに満ちた平穏な人生を歩みなさいと教えています。 今日から始まります新たな一年が体を安定させるための七戒と心を正しく保つための三戒を守る日々となり、仏教の教えに叶った毎日を過ごせるよう互いに支え合い助け合って精進を重ねて参りましょう。本日はご参拝頂き誠に有難う御座いました。 令和6年1月 天清寺 |
| 令和5年度の法話 |
12月の法話「人間の理想を目指して」
| 人間の理想を目指して 本日は寒い中ご参拝頂き有難う御座います。早いもので今年も師走を迎えましたが、皆様方にとりましては実り多い豊かな年だったのではないでしょうか。 修験道には錫杖を振り鳴らしながら唱える九条錫杖と言う経典があります。仏教の教えのポイントを簡潔にまとめた九条からなる短いお経です。今日はその中の第六条の教えについてお話させて頂きます。第六条では当願衆生 十方一切 無量衆生 聞錫杖声 懈怠者精進 破戒者持戒 不信者令信 慳貪者布施 瞋恚者慈悲 愚痴者智慧 驕慢者恭敬 放逸者摂心 具修万行 速証菩提と唱えます。和訳しますと「錫杖の音が聞こえたら自分を見つめて、至らないところがあれば正して行動を改めなさい。具体的には怠け者は精進努力に勤め、戒律を破る者は戒めを守るよう心掛けなさい。信仰心のない者は信心に努め、貪り物惜しみする者は物への執着を離れて人に施せるように努力しなさい。感情的で直ぐに怒る者は慈しみの心をもって人に接するよう努め、愚かで愚痴ばかりこぼしている者は教えを求めて善き師に近づき智慧を身に付けなさい。虚栄心が強くおごり高ぶる者は常に謙虚で慎みの心を忘れず、勝手気ままな者は心を正して自制に努め心を治めなさい。こうした修行に励み、速やかに悟りを開きなさい」となりますが、人間がもつ八つの欠点を具体的に取り上げ、理想的な人間を目指して勤め励みなさいと教えています。 どんな人にもどれか一つくらいは該当するものがあるのではないでしょうか。 これから始まります皆様方の今年最後のひと月が自分の欠点を改善できる日々となり、円満な心で新年を迎えることができますよう心よりご祈念申し上げます。本日はご参拝頂き誠に有難う御座いました。 令和5年12月 天清寺 |
11月の法話「二つの勝利に歓喜する」
| 本日はご参拝頂き有難う御座います。先日テレビを見ていましたら怒りを鎮める特集をしていました。あおり運転や顧客の優越的立場を利用した悪質なクレームが増大する社会情勢を考慮しての番組のようでした。番組では怒りは人間にとって生き残るための本能のようなものだと言っていました。敵と戦う時や逃げる時などの異常な力や走る速さなど、怒りによって超人的な能力が発揮されると言っていました。こうした時には大脳辺縁系の働きが活発になりアドレナリンが多量に分泌されるため、血液の流れが増大し脈拍が速くなって、そのような能力が発揮されるのだそうです。こうした体の異常な動きを抑制するのが前頭葉ですが機能するまでに3~5秒かかります。前頭葉が働き出すまでの間、上手く感情を抑えることができれば怒り狂うことなく冷静を保つことができると言うのです。そのためには深呼吸をしたり好きなものを思い浮かべるなどして気を落ち着かせる必要がありますが、番組では最も有効な手段として相手を応援する気持ちになることだと結論づけていました。相手を支援しようと思えば怒っていられなくなると言うのです。 これこそ仏教で説く慈悲の心なのです。仏教では人間の悩みや苦しみの根源は貪瞋痴の三毒にあると教え、貪りや怒り愚かさを諸悪の根源としているのです。三毒の一つである怒りはどのように解消すれば良いのでしょうか。「大安般守意経」では怒りを解消させる妙薬は慈悲喜捨の四無量心を起こすことだと教えています。慈とは慈しみの心で他者に楽を与えることです。悲とは他者の悩みや苦しみを取り除くことです。喜とは他者の喜びを自分の喜びとして共に喜ぶことです。捨とは他者に対する区別や差別を捨てることです。また、「雑阿含経」では怒る者に怒り返さぬ者は二つの勝利を得る。自分に勝つと同時に怒る相手にも勝利すると教えています。 これから始まります皆様方の新しいひと月が仏教の教えを守り、二つの勝利に歓喜できる日々となりますようご祈念申し上げます。本日はご参拝頂き誠に有難う御座いました。 令和5年11月 天清寺 |
10月の法話「人間国宝を目指して」
| 人間国宝を目指して 本日はお忙しい中、ご参拝頂き有難う御座います。猛暑が続いた夏も終わり自然は収穫の秋を迎えています。私達も自然に負けないよう実り豊かな人生を過ごして参りましょう。 大乗仏教では菩薩が行うべき修行として六波羅蜜を掲げています。波羅蜜とはサンスクリット語でパーラミターを音訳したもので、「完全」や「完成」を意味しています。菩薩になるため成し遂げなければならない六つの事とは布施・持戒・忍辱・精進・禅定・般若(智慧)です。具体的には困っている人には施しを行い常に戒めを守って、怒ることなく耐え忍び何事にも努力を続け、心を安定させて真理を見抜く智慧を身に付けることだと言えます。 波羅蜜の実践は法にかなった行為でなければならないことは勿論ですが、更に代償や見返りを求める行為であってはならないのです。そうした清く正しい気持ちで布施を行い戒めを守って日々努力を続け、腹を立てずに困難に遭遇しても耐え忍び常に心の安定を図って、目の前の事に囚われず道理にかなった生活を営む、これこそが菩薩を目指す波羅蜜修行と言えるのではないでしょうか。 まず自分で出来る事から始め、暗いニュースが毎日のように報道される今の世の中を少しでも明るくしたいものです。伝教大師最澄は黄金十両が国宝なのではなく、社会の一隅を照らす人こそが国宝なのだと明言されました。家庭や地域を明るく照らせる自分を目指して精進を重ねて参りましょう。それこそが本当の人間国宝と言えるのではないでしょうか。 これから始まります皆様方の新しいひと月が人間国宝を目指した日々となり明るく笑いに満ちた家庭や地域が実現するようご祈念申し上げます。本日はご参拝頂き誠に有難う御座いました。 令和5年10月 天清寺 |
9月の法話「なまぐさいと指摘されない自分を目指す」
| なまぐさいと指摘されない自分を目指す 本日はご参拝頂き有難う御座います。先月はお盆でしたし、今月は彼岸ですのでご家族お揃いでお墓参りをされたり、される予定の方も多いのではないでしょうか。仏前に肉や魚をお供えされる方はいませんが、こうした精進の習慣はインドにはなく、中国で考案され日本に伝来して精進料理を生み出しました。 仏教ではお釈迦様の時代から例え肉であっても自分のために殺したり、そうした疑いのあるもの、更には実際に殺すところを見たものでなければ食しても構わないとされていました。初期経典と言われますスッタニパータではなまぐさいとは肉や魚を食べる事ではなく、生きざまそのものを指すのであり身口意の三業そのものであると次のように教えています。「欲望を制することなく美味を貪り、不浄な生活をして虚無論を抱き、不正な行いをする人々をなまぐさいと言う。肉食をする事がなまぐさいのではない」また「怒りや驕りが強く、強情で反抗的、偽りを述べ嫉妬深く、高慢で不良なものと交わる人々をなまぐさいと言う。肉食する事がなまぐさいのではない」と説いています。そして、「ものを欲しがったり執着する心を離れ、わずかな時間もむなしく過ごすことなく勤め励みなさい。怠りは塵や垢である。怠りによって塵や垢が集積される。勤め励む事や叡智によって自分に刺さった矢を抜け」と精進の大切さを説いています。 日本では御岳精進(みたけそうじ)と言って吉野の金峰山に参詣する際には登拝に先立って精進潔斎を続け心身の浄化を図ることが平安時代から習わしになっていました。こうした習慣にならい私も奥駈修行に臨む際には酒や肉を絶って1か月間の精進潔斎に勤めましたが、供養や修行に際しては言動や行動、思いを正して心身の浄化を図り、少しでも神仏に近づけるよう努力する事が何より大切なのだと気付かされました。母や父の命日には仏教の教えを守り身口意の三業を慎み、心身の浄化を図ってお釈迦様に「なまぐさい」と指摘される事の無いよう精進を重ねて参りたいと願っています。本日はご参拝頂き誠に有難う御座いました。 令和5年9月 天清寺 |
8月の法話「言葉を貴重な宝に変える」
| 言葉を貴重な宝に変える 本日は暑い中、ご参拝頂き有難う御座います。先月は異常な暑さで日本中の方々が熱中症対策で大変な思いをされましたので、今月は涼しくなって欲しいと願うばかりです。 仏教では身口意の三業で悪業を作らず福徳を積んで、天界に赴けるよう勤め励みなさいと教えていますが、今日は三業の中でも日常生活で最も身近かな言葉についてお話させて頂きます。お釈迦様の教えを色濃く伝えている経典「スッタニパータ」では言動に関する教えを数多く説いていますので、その一つをご紹介致します。お釈迦様がヴァンギーサ長老に修行者としての言動に関する戒めとして次のように教えを説いています。 第一に最上の良い言葉を語れ 第二に理に反することを言うな 第三に好ましい言葉で語れ 第四に真実を語り偽りを語るな これを聞いた長老は「自分を苦しめず、他人を害さない言葉のみを語れ」との教えですねと要約しています。実に簡潔明瞭で、それでいて的を射た表現だと感じます。多くを語らず心して尊い言葉だけを発したいものです。 修行者に限らず相手を傷つけたり、不快にさせるなど、後になって後悔し結果的に自分を苦しめ悪業を作るような発言をしてはいけないのです。私達は夫婦や親子・友人など日常的に接する身近な人達に対し、深く考えもせず反射的に言葉を発していないでしょうか。ひと言ひと言に心を込め、その場に最もふさわしい慈愛に満ちた言葉で語れるよう気を配りたいものです。そうした努力を重ねることで発するひと言ひと言を価値ある貴重なものに変えることが出来、福徳を積むと同時に、自分を支えてくれている大切な人々をも幸福に出来るのではないでしょうか。 これから始まります皆様方の新しいひと月が金・銀・宝石にも勝る、価値ある貴重な言葉で満たされた日々となりますようご祈念申し上げます。本日はご参拝頂き誠に有難う御座いました。 令和5年8月 天清寺 |
7月の法話「仏教の在家信者として生きる」
| 仏教の在家信者として生きる 本日は暑い中、ご参拝頂き有難う御座います。 先月は仏教の信者としての生き方についてお話させて頂きましたので、今月は仏教の信者の中でも特に在家信者の生き方について勉強して参りましょう。お釈迦様は在家信者のダンミカに対し、出家修行者と同じ戒律を守って生活することは不可能なので、常に五戒を守り、斎日には八戒を守って生活するよう心掛けなさいと教えられました。 五戒とは不殺生戒・不偸盗戒・不邪淫戒・不妄語戒・不飲酒戒です。不飲酒戒では酒に酔ったことで悪事をなしたり怠惰になるなど、災いを引き起こす原因となる飲酒は回避しなさいと諭されました。斎日とは古代インドで神仏が私達の生活状態を監視する日とされていたため、特に生活を正して過ごす日だったのです。そのため斎日には五戒の他に夜は食事を取らない、装飾品で着飾ったり香水をつけたりしない、ベッドで寝ないと言う三つの戒律をも守って生活するようお釈迦様はお説きになられたのです。 お釈迦様はこうした戒律を守る生活を基盤にし、正しい方法で仕事に励み、それによって得た財を以て年老いた母と父を養い、勤め励んで怠ることなく生活しなければならないと善行の実践を奨励されました。更に自分で守るだけで終わらず縁ある方々にも守ってもらえるよう努力しなければならないと説かれました。そして、こうした教えを守って暮らした在家信者は死後、自ら光を放つ神々の世界に赴くことが出来るのだと説かれました。 これから始まります皆様方の新しいひと月が在家信者の生き方に叶った毎日となり、死後、天界に往生できますよう心よりご祈念申し上げます。本日はご参拝頂き誠に有難う御座いました。 令和5年7月 天清寺 |

6月の法話「仏教の信者として生きる」
| 仏教の信者として生きる 本日はお忙しい中、ご参拝頂き有難う御座います。早いもので今年も半年が過ぎようとしています。一日一日を大切に生きたいと誰しも願っていますが、具体的にはどのように生きれば良いのでしょうか。 仏教は人の生き方を説く宗教とも言えますが、パーリ経典の相応部では仏教の信者としての生き方を具体的に教えています。そこでは仏教の信者とは戒律を守り、信仰心あつく、布施を行い、正しい智慧を持っている者のことだと説いています。 そして、具体的には守るべき戒律とは在家信者に課せられた不殺生などの五戒を指し、信仰心とは仏教の教えを信じることであり、布施とは貪りを離れ慈悲の心で必要としている人に必要なものを施すことであり、正しい智慧とは縁起の道理を理解し、諸行無常を悟ることだと教えています。 このように仏教の信者であるものは、まず信を確立して、それに基づき戒律を守り、布施を実践して悟りに導く智慧を体得しなければならないとしています。このように全ての根源となる信を最も大切なものとし、信には懺悔と随喜と祈願の三つが包含されているとしています。具体的には常に自分を省みて犯した罪や汚れを自覚し反省すること。また、他者の幸せを常に願い、人の幸せを自分の幸せとして受け止めて共に喜び、仏のように正しく生きたいとの願いを常に抱いて行動することだと説いています。 こうした仏を信じ正しく生きようとする心を仏性と呼び、誰にも備わっているにもかかわらず煩悩によって覆い隠されているため、仏の心を発揮できず悩み苦しんでいるのだと教えています。 これから始まります皆様方の新しいひと月が煩悩を解消して、授かった仏性を存分に発揮でき、極楽浄土につながる毎日となりますようご祈念申し上げます。本日はご参拝、誠に有難う御座いました。 令和5年6月 天清寺 |
5月の法話「全ては心が作る」
| 全ては心が作る 本日はゴールデンウイークの中、ご参拝頂き有難う御座います。今年は1日と2日を休みますと9連休になりますので、ご家族お揃いで海外旅行にお出掛けになられた方も多いのではないでしょうか。 華厳宗の根本経典とされます「華厳経」には「牛は水を飲んで乳を成し、蛇は水を飲んで毒を成す」とあります。この教えは飲んだ水そのものに問題があるのではなく、水をどのように扱うかによって出来上がったものが全く反対の働きをしてしまう程、大きく変化する事を私達に教えてくれています。 牛は水を飲み、それを子牛の命を守り元気に育てるための栄養ある乳にして出し、蛇は水を飲んでもそれを敵対するものの命を奪うための毒にして出すのです。同じ水を飲んでいながら、どうして結果にこのような違いが出来てしまうのでしょうか。 現存する最古の経典とされます「ダンマパダ」には「物事は心に基づき、心を主とし、心に依って作り出される。もしも清らかな心で話したり行ったりするならば福楽がその人につき従う。車を引く牛の足跡に車輪がついて行くように」とあり、言動や行動はどのような思いで行うかによって、その結果が決まってしまうと説いています。 乳を出す牛には親としての子牛への愛情があり、毒を出す蛇には相手を征服しようとする敵愾心があります。この心の違いが水によって作り出される液体の質や価値を大きく変える原因になっているのです。私達の日常生活でも同じ事が言えるのではないでしょうか。毎日の生活で体験する一つ一つの出来事をどのような心で受け止め対処するかによって、生活の質や価値そのものが大きく変ってしまうように感じます。 これから始まります皆様方の新しいひと月が牛のように自分に授かった仏の心(仏性)を存分に活かして、有縁の人々を喜ばせ幸せに出来る徳積みの日々となりますよう御祈念申し上げます。本日はご参拝頂き誠に有難う御座いました。. 令和5年5月 天清寺 |
4月の法話「三力の統合を願う」
| 三力の統合を願う 本日は貴重な週末、ご参拝頂き有難う御座います。4月は卒業や就職・転勤など一年の中でも新たな出発を迎える門出の月と言えます。門出に際し志も新たに様々な願いを抱かれた方も多いのではないでしょうか。 密教は衆生救済の実践を目指す宗教ですが、その中心的な思想を示す重要な経典の一つに「大日経」が有ります。「大日経」の悉地出現品では衆生救済を目指し、諸願を成就させようとするならば三種の力を統合出来るよう念じなさいと教え、三力偈の読誦を掲げています。密教の戒律とも言われる三昧耶戒を遵守する事はこの三力偈に象徴される三種の力の統合を図って、悩み苦しむ衆生を救済する為の力を創出し身に付ける為の修行の実践と言えるのではないでしょうか。 三力偈とは「以我功徳力 如来加持力 及以法界力」の三つの力を掲げる非常に短い偈文です。この三力偈では心願を成就させる為には先ず本人の努力や徳分が必要であり、そうした衆生救済を目指す清浄なる願いに如来などの見えない加護の力や様々な縁とも言うべき法界の力が加わって実現出来るのであり、そのバランスと統合された力が大切だと教えているのです。このように三力偈では自力でも他力でも無いバランスの取れた総合的な力を発揮できて始めて心願の成就が実現するのだと教えています。 二番目の「如来加持力」や三番目の「及以法界力」をどのように捉えるかによって修行の仕方や進むべき道に違いが生じる事になります。行者の末期は惨めだと良く言われますが三力偈は霊感や自分の法力を過信して自ら身を滅ぼす事のないよう、衆生救済に際して最も大切な心構えを教えてくれているように思われます。 とは言っても衆生を救済する力の根源となる最も大切なものは自らの身口意による善行であり、家族のため地域や社会のためにと自分の事をさておき皆の幸せを願い、困っている人の救済を目指そうとする菩提心そのものではないでしょうか。これから始まります皆様方の新しいひと月が三力偈に象徴されます三種の力を菩提心により統合でき、諸願を成就できる日々となりますようご祈念申し上げます。本日はご参拝頂き誠に有難う御座いました。 令和5年4月 天清寺 |
3月の法話「彼岸を機に自分を見つめる」
| 彼岸を機に自分を見つめる 本日は雪の中ご参拝頂き有難う御座います。 早いもので今年もお彼岸を迎える季節となりました。お彼岸の習慣は日本独自の仏事でインドや中国には御座いません。日本では浄土信仰が広がる中で太陽が真東から昇り真西に沈む春分の日と秋分の日を西方極楽浄土に往生したご先祖を最も身近に感じる日として彼岸会を執り行う習慣が生まれました。 古くから日本には亡くなった人の霊魂は肉体を離れて神々のすむ近くの山にのぼり祖霊となって、里村で暮らす子孫を見守り様々な恩恵をもたらしてくれるとする祖霊信仰が有りました。こうした習慣が仏教の浄土信仰と融合してお彼岸の供養と言う日本独自の仏事を生み出したのです。 お釈迦様が存命だった頃の話ですが、毎日忙しく働き続けて満足な信仰も出来ずに若くして亡くなった息子が天国に生まれる事が出来、安楽に過ごせるようになるでしょうかと在家信者の母親が尋ねたのに対し、お釈迦様は常に東へ東へと伸びて成長を続けた大木はどんな切り方をしても東に倒れる。それと同じように正しい生き方をしていた人は必ず天界に赴き良い所におさまる事が出来ると応え母親を安心させたと言うのです。 また、他人を傷つけたり物を盗むなど罪深い生き方をしていた人の例では湖に大きな石を投げ入れて「石よ浮かび上がれ」と幾ら願い祈ったところで石が浮かび上がらないように、天界に生まれる事はなく永い間苦しむ事になると述べ、生前の生き方がいかに大切であり、それによって死後の世界が決まってしまうのだと説かれました。 私達がこうして毎日元気に過ごせるのは両親を始め多くのご先祖のお陰なのです。お彼岸を機に両親やご先祖に感謝の祈りを捧げましょう。そして、自分の生き方を冷静に見つめ、死後は天界に生まれる事が出来るとお釈迦様に言って頂けるように日々精進を重ねて参りましょう。 本日はご参拝頂き誠に有難う御座いました。 令和5年3月 天清寺 |
2月の法話「六方を拝して道を守る」
| 六方を拝して道を守る 本日は雪の中、ご参拝頂き有難う御座います。今年こそ仏教徒として教えに従った生活をしたいものだと願っていますが、在家信者の生活規範を説いたとされる六方礼経では以下のように教えています。 お釈迦様が托鉢に出掛けていると沐浴して衣服を整え東西南北と天地の六方を礼拝している青年に出会いました。お釈迦様が何故六方を礼拝しているのか尋ねると青年は家が栄えるように亡き父の教えを守って礼拝していると応えました。そこでお釈迦様は父親が六方を礼拝せよと教えた本当の意味を青年に説いて聞かせたのです。 東とは親子、西は夫婦、南は師弟、北は友人、地は使用人、天は沙門やバラモンの道を示しているのであり、それぞれの道を正しく歩み円滑な人間関係を維持して保つならば、自ずと家は栄え家系は発展するのだと教えました。そして、こうした六つの道を守る事が出来て始めて、亡き父が教えてくれた六方拝を実践した事になるのだと諭したのです。具体的には親子関係では子供は親に対して年老いたら養い、家業を継ぎ家督を相続して先祖を供養しなければならない。これに対し親は子供を悪から遠ざけ善を積ませて、適齢期になれば結婚させ時機を見て家督を継がせなければならない。夫婦関係では夫は妻に対し尊敬の念を抱き軽蔑したり浮気する事無く、家事を任せて時には装飾品を買って与えなければならない。これに対し妻は親族の調和を図って貞操を守り、財を浪費せず家事に精を出さなければならない。師弟関係では弟子は師を礼拝して迎え熱心に教えを聞き、師を信じて敬わなければならない。これに対し師は親切に教え導き弟子を褒めたたえて常に守護しなければならない。友人関係では友を欺く事無く相手が逆境に陥った時には相談に乗り、共に支え合って守ってやらなければならない。雇用関係では雇用主は使用人に対し能力に応じた仕事を与えて食料や給料を支給し、病気の時には看病を怠らず疲れの状況を見て休みを与えなければならない。これに対し使用人は雇用主より早く起き遅く寝て仕事に励み、主人を批判せず称讃しなければならない。沙門やバラモンとの関係では身口意の三業を整えて迎え、教えを守り財物を施与しなければならない。これに対し沙門やバラモンは道を説いて聞かせ、善を積ませて安楽な境地に導かなければならない。 以上のようにお釈迦様は六方を礼拝するとは単に災難を逃れるために行うのではなく、人間としての道を守って生活する事により自分を取り巻く環境が整い、その結果として災いが遠のき豊かで平穏な人生を送る事が出来るようになるのだと諭したのです。このように仏教とは苦しみ多きこの世の人生をいかに人間らしく正しく生きるかを教えているのです。このような尊い教えにご縁を頂けた事に感謝しましょう。そして、その教えを毎日の生活の中で一つでも多く実践できるよう精進を重ねて参りましょう。 本日はご参拝頂き誠に有難う御座いました。 令和5年2月 天清寺 |
1月の法話「水の如く徳行を積む」
| 本日は雪の中ご参拝頂き有難う御座います。 皆様方の今年一年が実り多い豊かな年になりますように祈りを込めまして護摩を焚かせて頂きました。私も今年こそ初心に立ち返りお釈迦様の教えや菩薩行の基本となる自利利他行の実践に精進を重ねて参りたいと願っています。 仏教の教えを守り功徳を積む仏道修行に励むとは水のように生きる事ではないでしょうか。お釈迦様は怠る事無く勤め励めと申され、「自灯明 法灯明」として真理に従いつつも自分を拠り所として生きる事をお説きになられました。大乗仏教では菩薩行の根幹をなすものとして自利利他行を掲げ、己の力を養いその力を以て悩み苦しむ衆生の救済を目指しなさいと教えています。 水は自ら下へ下へと低い所を求めて精進を続け、常にへり下って高い所から見下すような事はしません。また、水は丸い器に入ると丸くなり、四角い器に入ると四角くなってどんな形の器にも従い争う事をしませんが、決して自分の性質を失う事がありません。そして時には周囲の環境に従い液体から気体や固体へと大きくその姿を変えますが自分の本性を失う事はありません。更に水は生きとし生けるものに対し生命の維持に欠く事の出来ない恵みを与えていながら恩をきせたり自慢したりしません。 老子は「上善は水の如し」と述べ人間にとって最善の生き方とは水のように振る舞う事だと表現しましたが、まさにその通りだと痛感致します。 これから始まります新しい一年が水のように振る舞う事が出来る日々となり、功徳を積む仏道修行実践の毎日となりますよう互いに精進を重ねて参りましょう。本日はご参拝頂き誠に有難う御座いました。 令和5年1月 天清寺 |
天 清 寺
〒038-0031
青森県青森市三内丸山326-5
TEL 011-764-2328.